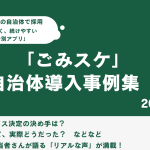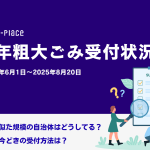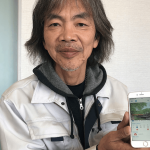今回は、自治体指定ごみ袋でよく使われる袋の素材について特集しました。ポリエチレンを用いた袋が主流でしたが、近年は環境を意識したバイオプラの製品を採用する自治体も増加傾向にあります。ここでは指定袋の素材選定でよく耳にする素材をご紹介していきます。
■ポリエチレン
原料の原油から「ナフサ」を精製し、加熱することで、ポリエチレンの元となる「エチレン」を発生させます。その後高温・高圧化で化学反応を起こすことで完成します。
①HDPE(高密度ポリエチレン)
「ハイデン」と略される材質で、密度が0.942~0.970のポリエチレンです。袋をこすり合わせるとカシャカシャした音が鳴るのが特徴です。伸びは比較的少ないので、生ごみなど少し重みのあるものを入れる可燃ごみ用指定袋に使われることもあります。また、スーパーやコンビニなど小売店のレジ袋としても使用されています。

②LDPE(低密度ポリエチレン)
「ローデン」と略される材質で、密度が0.910~0.930未満のポリエチレンです。 つるつるしていて柔らかい触感があります。透明度があり、伸びが良いことが特徴。固いもの、尖ったものを入れる燃えないごみ用指定袋に使われることもあります。 また、工場から出荷される工業製品の保護包装をはじめ、食品用、農業用の保護包装など、様々なシーンで使用されています。

■バイオプラ
バイオプラスチックは、植物などの再生可能な有機資源を原料とする「バイオマスプラスチック」と微生物等の働きで最終的に二酸化炭素と水にまで分解する「生分解性プラスチック」のことを指します。
③バイオマスプラスチック
再生可能な有機資源(サトウキビ、トウモロコシ、トウゴマなど)を利用することで限りある石油資源の使用を抑え、さらにカーボンニュートラルの考え方(燃やしても植物が吸収した分の二酸化炭素が排出されるだけで地球上の二酸化炭素総量が増えないまたは同じ量という考え方。)により、環境に優しいとされています。
④生分解性プラスチック
約7割はバイオマス由来、その他は化石資源由来のナフサを主な原料として製造されています。
微生物等によって比較的短時間でCO2と水にまで分解されるという大きな特徴があり、環境中のプラスチックごみ量の削減ができる素材です。製品としての強度が比較的低く、分解が進むため保存期間が短くなりますが、環境に優しい素材として注目されており、生ごみ回収袋等に使用されている例もあります。

■2種類のマークについて
・「バイオマスマーク」:一般社団法人日本有機資源協会(通称:JORA)※四つ葉のクローバーマーク
生物由来の資源(=バイオマス)を利用し、品質および安全性が関連する法規、基準、規格等に適合している商品に使用されています。
・「バイオマスプラマーク」:日本バイオプラスチック協会(通称:JBPA)※BPのマーク
バイオマスプラ識別表示制度によって承認されます。バイオマスプラとは、再生可能なバイオマス(植物等)由来有機物質をプラスチック構成成分として所定量以上含む、バイオマスプラスチック製品のこと。
最後に
今回は指定袋によく使われる素材を4つ取り上げました。選択肢が増えてきていますので、地域の実情に合わせた素材探しの一助にしていただけますと幸いです。