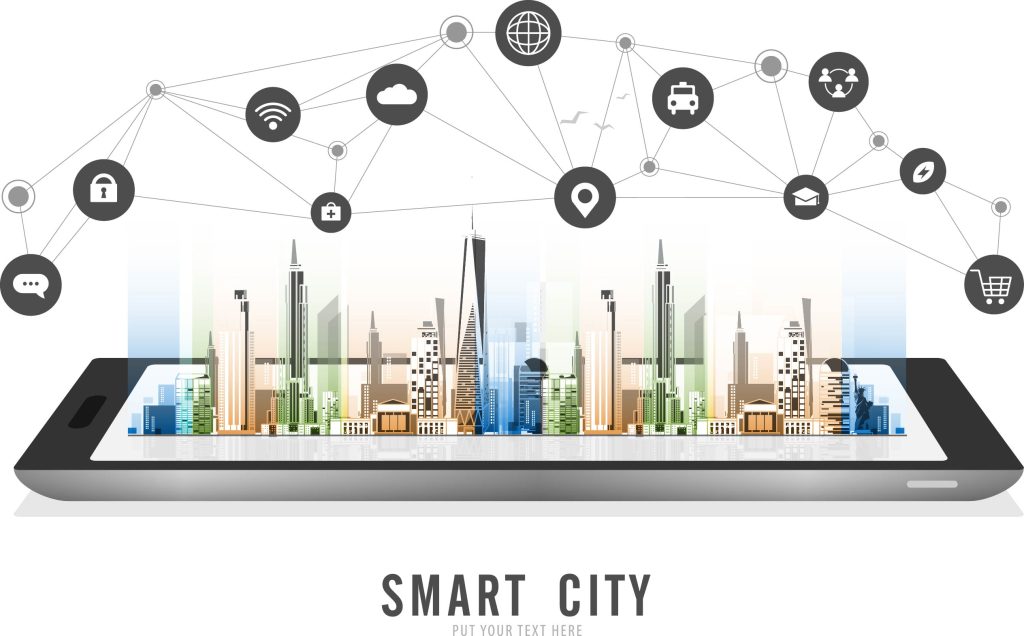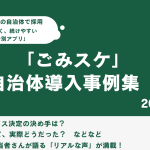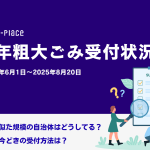スマートシティへの取り組みが加速しています。新しい技術を活用したスマートシティの構想は、公民ともに今後さらに注目されていくでしょう。
この記事では、スマートシティの概要や利点、今後の展望などについて、取り組み事例を交えながら詳しく解説します。
スマートシティとは

スマートシティは政府が主導する持続可能な環境都市の構築を指しています。概要や目標、メリットなどについて見てみましょう。
スマートシティの概要
内閣府や国土交通省は、平成30年8月にリリースした「スマートシティの実現に向けて」にてスマートシティの定義を示しています。同資料によると、「先進技術を活用した持続可能な都市」を目指す概念です。
※参考:スマートシティの実現に向けて/国土交通省都市局 P2-3
スマートシティはICTやAIといった先端技術を駆使した都市が該当します。具体的にはエネルギーや交通、行政サービスなどのインフラを、効率的、かつ、最適化された形で整備・運用することにより、持続可能かつ環境配慮型の特性を持つ都市です。
技術革新と持続可能性が融合した新しい都市モデルは、未来の都市開発が現実になったといっても過言ではありません。スマートシティの機能によって市民の生活の質を向上させ、生活環境を便利で快適にすることが期待されています。
スマートシティの目標
スマートシティの大きな目標は、都市化にともなう課題を解決し、環境変化に柔軟に適応しながら、誰にとってもよい生活を持続的に向上させることです。
日本では人口減や高齢化、渋滞などさまざまな社会的課題があります。そのような課題に対処するため、「未来投資戦略 2018-Society 5.0(ソサエティ5.0)」において、「次世代の街づくり」としてスマートシティ構想が取り入れられました。
※参考:未来投資戦略 2018-Society 5.0(ソサエティ5.0)/首相官邸 P8
スマートシティ構想では、ビッグデータを駆使して交通網を見直し、再生可能エネルギーの活用をはじめ、多岐にわたる施策を官民協力で進めることが推進されています。
スマートシティのメリット
スマートシティの実現には多数のメリットがあります。
まず、持続可能な都市を実現できる点です。効率的なエネルギーの利用や再生可能エネルギーの導入、交通網の最適化などが融合することにより、環境への負荷を軽減し、生態系や資源の保護が可能になります。
また、防災や減災にも大きな効果が見込まれています。センサーやリアルタイムで収集したデータの活用により、自然災害や災害時の避難誘導の迅速性や正確性が向上し、被害を最小限に食い止めることが期待できるでしょう。
さらに、ビジネスチャンスの創出する可能性も見逃せません。新たな技術やサービスの導入により、産業の多様化や新しいビジネスモデルの形成が可能になります。地域経済の活性化、雇用機会の拡大など、多方面でのメリットが生まれるでしょう。
スマートシティとスーパーシティの違い
スマートシティは、既存の課題を解決するために、部分的にIT化を進める「課題解決型」のアプローチです。個別の分野ごとにできることから進めていきます。
一方、スーパーシティは未来の理想的な社会像を描き、それを実現するために技術や制度をゼロベースで構築する「未来社会先行実現型」のアプローチと言えます。複数分野のスマートサービスを同時に実装し、一気に実現していくことに焦点を当てています。また、「都市OS」と呼ばれるデータ連携基盤の導入も大きな特徴です。これにより、交通データやエネルギーデータなど、分野ごとのデータが連携され、AIが都市全体の最適化を図ることができます。スマートシティもデータの活用は行いますが、スーパーシティのように複数分野のデータを一元的に連携させる「都市OS」の概念は、よりスーパーシティに特有のものです。
これらの違いを理解することで、都市の未来に向けた適切な選択が可能となります。実践的なポイントとして、スーパーシティの実現には長期的なビジョンと法整備・大規模な投資が不可欠であり、地域社会の全面的な協力が求められます。
ブラウンフィールド型とグリーンフィールド型
■ブラウンフィールド型のスマートシティ
ブラウンフィールド型のスマートシティとは、既存の都市インフラや建物を活用しながら、最新のICT技術を導入して都市の効率化と生活の質向上を図る取り組みです。これにより、都市開発の際に新たに土地を開発するグリーンフィールド型に比べ、環境への負荷を軽減しつつ、迅速かつ経済的にスマートシティを構築することが可能です。例えば、既存のビルにスマートメーターやエネルギー管理システムを導入することで、エネルギー効率を向上させる取り組みが行われています。また、公共交通機関の運行データをリアルタイムで管理し、運行の最適化や渋滞の緩和を実現するケースもあります。こうした既存インフラの効果的な活用は、資源の節約につながり、持続可能な都市開発を推進します。
■グリーンフィールド型のスマートシティ
グリーンフィールド型のスマートシティとは、既存の都市やインフラを活用するのではなく、新たに土地を開発してゼロから設計される都市モデルを指します。このアプローチでは、最先端の技術を最大限に取り入れ、エネルギー効率や持続可能性、住民の生活の質を向上させることが可能です。例えば、交通インフラは自動運転車や電気車専用の道路網を設計し、エネルギーは再生可能エネルギーを基盤とした分散型システムを採用することが考えられます。ただし、完全に新しい土地を開発するため、資金や時間が大量に必要となる点には注意が必要です。このような都市は、未来の理想的な生活環境を目指し、持続可能な社会の実現に貢献します。
具体的な取り組み例
スマートシティへの取り組みはすでに各方面で始まっています。取り組み例の一部をご紹介します。
スマートホーム

スマートホームは、子育て世代や高齢者、単身者など、幅広い層のライフスタイルやニーズに合わせたIoTサービスを提供する新しい生活概念です。
たとえば、家電製品をインターネットで連携させ、スマートフォンや音声でコントロールすることもスマートホームの一例です。エネルギーの無駄を削減し、光熱費の節約が可能となるとともに、複雑な操作が不要になる一面も持っています。
スマートホームはすでに浸透が進んでいます。スマートフォンを通したリモートコントロール、スマートスピーカーの音声認識、自動ロックや防犯カメラの導入、省エネ機能を備えた照明など、すでに利用している人も多いのではないでしょうか。
スマートグリッド
スマートグリッドとは、送配電網に専用のソフトウェアやIT機器を組み込んだ電力ネットワーク供給システムです。電気の供給と需要を双方向でコントロールできる構造になっています。
例としては、一般家庭や企業で使われているスマートメーターが挙げられます。電気使用量をデータ送信することにより、リアルタイムでエネルギーの需要・供給が把握できる仕組みです。効率的な送電やトラブルの把握が可能になり、電力の安定供給につながります。
交通のスマート化
交通のスマート化は、街中に配置されたカメラやIoTデバイスから得られるデータを活用するシステムです。
具体的には交通センサーやカメラを通じて、渋滞や事故の情報をリアルタイムで把握し、適切なルート案内や交通制御を行います。
交通のスマート化により、市民は移動がスムーズになります。最適な経路を選択しやすくなるため、移動にかかるコストの節約が実現するでしょう。
効率的な移動の促進は、都市の交通インフラを最適化する一環として、現代都市の社会的課題に対応する重要な取り組みです。
廃棄物管理のスマート化
廃棄物管理のスマート化では、IoT技術を活用し、ごみ収集所の蓄積量を測定し、データの取得がおこなわれます。リアルタイムなデータ収集により、ごみ収集の効率が向上し、不要な廃棄物の発生を減らすことを通し、環境への負荷を抑える効果も期待されます。
自治体や民間の廃棄物処理業者が適切なタイミングでごみを回収したり、市民がごみ処理場を効率的に利用したりできるようにすることも重要です。すでにサポートサービスが開発されており、インターネットやスマートフォンアプリを利用した粗大ごみ受付管理システムを導入した自治体もあります。
実現に重要な「技術・インフラ」について
スマートシティの実現には、技術・インフラの活用が不可欠です。ここでは活用方法について詳しく解説します。
ICTとAI技術の活用
スマートシティの実現において、ICT(情報通信技術)とAI(人工知能)は重要な役割を果たします。ICTは、データの収集、共有、分析を可能にし、都市全体の効率を向上させます。具体的には、公共交通機関の運行管理やエネルギー消費の最適化、さらには市民サービスの提供などに活用されます。一方、AI技術は、大量のデータを分析し、予測や自動化を実現します。たとえば、AIを用いた交通渋滞の予測や、異常気象時の迅速な対応などが挙げられます。
これらの技術を効果的に活用するためには、技術の導入だけでなく、住民や市職員のリテラシー向上も重要です。ICTとAIがもたらす利便性を最大限に引き出すことで、スマートシティは住民にとってより快適で安全な環境を提供できるのです。
スマートシティを支える最新技術
スマートシティを実現するための最新技術には、主にIoT(モノのインターネット)、ビッグデータ解析、AI(人工知能)、および5G通信が挙げられます。まず、IoT技術は、街中の様々なセンサーやデバイスをインターネットに接続し、リアルタイムでのデータ収集を可能にします。これにより、交通の流れを最適化したり、エネルギー消費を効率化したりすることができます。次に、ビッグデータ解析は、収集した膨大なデータを分析し、住民のニーズに合ったサービスを提供するために役立ちます。さらに、AIはデータからの予測や自動化を実現し、例えばスマート交通システムでは、渋滞の予測や事故の防止に寄与します。最後に、5G通信は、これらの技術を支える高速かつ低遅延の通信基盤を提供し、スマートシティのインフラをより安定させます。これらの技術を組み合わせることで、スマートシティはより効率的で持続可能な都市環境を築くことが可能です。
スマートシティの未来展望

スマートシティを推進することは、どのような未来展望につながるのでしょうか。エネルギー面、生活面、地域社会、環境保全など、多方面での発展が期待されています。
エネルギー効率の向上
スマートシティの未来展望において、建物や家電製品のエネルギー効率の向上は重要です。断熱性能の向上やLED照明の導入など、エネルギーの無駄を減少させ、環境への負荷を軽減するさまざまな取り組みが行われています。
とくに日本では、太陽光発電システムと蓄電池ユニットを組み合わせたスマート住宅の標準化が進んでいます。標準化の促進は、自家発電や蓄電を活用した住宅単位でのエネルギーの効率性向上が見込まれる注目の要素です。
生活の利便性向上
都市の機能やサービスを効率化・高度化し、生活の利便性が向上することもスマートシティの未来展望における重要な課題です。
前述の通り、ICT技術を活用したスマートホームの導入や、スマートフォンアプリを活用した交通情報提供などがすでに進行しています。従来よりも利便性を感じるようになった層も増えていることでしょう。今後も大きな発展が期待される分野です。
地域社会への貢献
地域社会への貢献にも期待が寄せられています。生活の質向上、防災・減災、交通状況の改善など、地域にはさまざまな課題が存在しますが、新しい技術の活用により、対処しやすくなると考えられるためです。
データ分析やセンサーネットワークを通じて得られる情報は、地域の課題を的確に把握し、迅速で効率的な解決策を導き出す有用な手段です。また、そのようなサービスの事業化によって地域の新たな雇用創出も期待されています。
環境保全の推進
スマートシティの未来展望では、環境保全の推進も重要視されています。新しい技術を活用した環境システムでは、リアルタイムで情報を分析し、環境保全行動につなげられる強みがあると考えられています。
たとえば、空気や水の質などの環境情報をセンサーなどで収集し、異変が検知された場合には即座に対応できるシステムを構築すれば、都市のインフラ維持で非常に重要な役割を果たせます。
環境の変化に敏感に対応できるということは、早期の問題解決が可能となり、住みよい都市環境確立の推進につながるでしょう。
国内外の取り組み事例
スマートシティへの取り組みについて、国内外の事例を見てみましょう。
国内のスマートシティ事例
【東京都板橋区】
日本の食品ロスは年間600万トンにもおよび、長年問題視されている大きな課題です。東京都板橋区では、食品ロスを減らし、有効活用するサービス「いたばし×タベスケ」に取り組みました。
賞味期限、消費期限が近い食品は、従来なら廃棄の可能性が高くなるのですが、価格を下げてタベスケのサイトでアピールすることにより、その食品を必要とする人が手軽に購入しやすいシステムが構築されています。
【大阪府箕面市】
大阪府箕面市では、自治体の廃棄物回収をサポートするサービス「ソダイシス」を導入し、スマートフォンから粗大ごみの持ち込みを予約・管理できるシステムを構築しました。
従来のアナログシステムでは効率的な予約処理ができず、市民がごみを持ち込んだ時点で2時間もの待ち時間が発生することもありましたが、導入後は待ち時間の短縮や混雑の解消が実現しています。
海外のスマートシティ事例
【スペイン・バルセロナ】
スペイン・バルセロナでは2000年代から街中にセンサーを設置し、データを収集するシステム「センティーロ」を運用しています。
収集されたデータは水道システムの管理や街灯のコントロール、交通渋滞のコントロールなどに活用され、無駄なエネルギーの削減やスムーズな交通環境の実現につながりました。
【シンガポール】
シンガポールでは3D技術を活用した「バーチャル・シンガポール」が導入されました。地形、交通インフラなど、国土全体を3D化し、リアルタイムでデータを収集するシステムです。
また、多彩なシミュレーションができる機能も搭載されています。これにより、交通や環境の管理や適切な誘導、発電量のチェックなどが可能になり、人々の生活の質向上において大きな貢献を果たしました。
日本政府の取り組み
日本政府ではスマートシティ推進体制を構築し、データ利活用型スマートシティ事業をおこなう地方公共団体や企業向けに初期投資や体制整備のサポートを打ち出しています。
また、スマートシティ推進のため、官民連携プラットフォームも発足しました。民間企業や研究機関、地方公共団体などが会員となり、さまざまな業種が参画しています。
民間企業の取り組み
【NTTコミュニケーションズ】
NTTコミュニケーションズは「BizCITY」を開発・提供しました。高い信頼性とセキュリティを備えたネットワークと、必要なソフトウェア機能のみを提供するSaaS(Software as a Service)の包括的なサービスです。
スマートシティの構築にはなくてはならない優れたサービスは、今後の日本におけるスマートシティ推進を力強くサポートするでしょう。
【川崎重工業株式会社】
川崎重工業株式会社では、5Gを活用した自動配送ロボットの開発を進めています。将来的な運用に向け、2022年1月には実証実験がおこなわれました。
効率的な配送システムの構築はスマートシティの実現に不可欠です。実用化に向け、技術面、運用面、事業面における課題の解消が期待されています。
スマートシティ普及における課題
スマートシティの普及にはいくつかの課題が存在します。代表的なものをご紹介します。
インフラの整備とコスト
スマートシティの実現には、インフラの整備が欠かせません。これは、都市の機能を支える基本的な構造を最新の技術でアップグレードすることを意味します。例えば、センサー技術を活用した交通管理システムや、エネルギー効率の高い街路灯の導入が挙げられます。これにより、都市の運営が効率化され、環境負荷の軽減や住民の生活向上が期待されます。しかし、こうしたインフラの整備には多額のコストが伴います。自治体は、限られた予算の中で優先順位を決め、民間企業との協力を模索する必要があります。具体的には、公共と民間のパートナーシップを活用した資金調達や、長期的な視点でのコスト効果分析が求められます。スマートシティを成功させるためには、技術投資の価値を明確にし、住民の理解を得ることが重要です。
プライバシーとセキュリティの課題
スマートシティの実現に向けては、プライバシーとセキュリティの課題が重要なテーマとなります。多くのデータがリアルタイムで収集・解析される状況では、個人情報の保護が不可欠です。データの不正使用やサイバー攻撃のリスクを最小限に抑えるため、自治体は高度なセキュリティ対策を講じる必要があります。具体的には、データの匿名化や暗号化技術の導入、厳格なアクセス制御の設定が考えられます。また、住民の信頼を得るためには、透明性のあるデータ管理方針を示し、プライバシーに関するガイドラインを整備することが求められます。
技術的課題
スマートシティの実現においては、いくつかの技術的課題が存在します。まず、膨大なデータを収集・分析するためのインフラが必要です。このインフラは、データのリアルタイム処理を可能にするために、高度なネットワーク技術と大容量のデータストレージを備えている必要があります。また、システムの相互運用性も重要です。異なるベンダーの技術やシステムが一貫して動作するようにするためには、標準化されたプロトコルの導入が求められます。さらに、サイバーセキュリティの対策も不可欠です。スマートシティでは多くの個人情報が扱われるため、データの保護とプライバシーの確保が求められます。これにより、住民の信頼を得ることができ、持続可能な都市運営が可能となります。これらの課題を克服することで、スマートシティはより効率的で住みやすい環境を提供できるのです。
法律や規制の問題
スマートシティの導入においては、法律や規制の問題が重要な課題となります。これらは、技術の進化に伴い、個人情報の保護やデータの取り扱いに関する法律が追いついていない場合があるためです。例えば、都市の監視カメラやセンサーから収集されるデータの利用については、適切なプライバシー保護の規制が必要です。日本では、個人情報保護法や情報通信技術に関する法令が存在しますが、これらをスマートシティに適用する際には、特定の事例に応じたガイドラインや規制の策定が求められます。また、自治体がスマートシティを推進する際には、住民の理解と協力を得ることが不可欠であり、法律に関する正確な情報提供と透明性が重要です。これにより、住民の信頼を築き、持続可能なスマートシティの運営が可能となります。
社会的課題
スマートシティの推進に伴い、社会的課題の解決が求められています。まず、都市化の進展による交通渋滞や環境汚染といった問題があります。これに対し、スマートシティでは、自動運転技術や電動バスの導入を通じて、交通の効率化と排出ガスの削減を図っています。また、高齢化社会に対応するため、遠隔医療や見守りサービスの導入が進められています。これにより、高齢者が安心して暮らせる環境を提供し、医療資源の効率的な活用が可能となっています。さらに、デジタルデバイドの解消も重要な課題です。地域間の情報格差を埋めるため、公衆Wi-Fiやデジタル教育プログラムの拡充が行われています。これらの取り組みは、住民の生活の質を向上させるだけでなく、持続可能な都市の実現に貢献しています。
まとめ
スマートシティの実現は、都市生活をより快適で持続可能なものに変える大きな可能性を秘めています。基本的な考え方として、情報通信技術を活用して都市の効率を高めることで、エネルギーの削減や交通の円滑化が図られます。具体的な事例として、スマートメーターの導入によるエネルギー管理の高度化、交通センサーによる渋滞緩和策などがあります。
これらの取り組みが成功するためには、市民の理解と協力が不可欠です。自治体は、プロジェクトの透明性を保ちつつ、市民参加を促進することが重要です。スマートシティが実現する未来は、多くの人にとってより良い生活を約束するものであり、そのための準備を進めることが求められています。