マイナンバーの取得率が高くなった今、広い範囲でマイナンバーの活用が進んでいます。実際にマイナンバーを利用した新システムの導入・運用する自治体も増加しています。
防災もそのひとつです。災害時、被災者支援業務をスムーズにおこなえるように開発された避難所受付システムや情報共有システムが注目されています。
本記事では、防災面でのマイナンバー活用や、実際に導入された活用事例や課題、新規導入時の流れなどについて詳しく解説します。

国が進める「マイナンバーカードの利活⽤拡⼤」について

平成28年、マイナンバー制度がスタートし、マイナンバーカードの取得が進むと令和5年11月には取得率が全国民の72.8%に達しました。
現在、国はマイナンバーを活用したさまざまなシステムやサービスの導入を推進しています。
具体的な政策等
マイナンバーの活用は、人々の生活に関わる広い分野で進められています。
まず、各種カードや資格証明書のデジタル化です。マイナンバーカードの電子証明書は多種の資格や個人情報と紐づけられるようになり、情報確認が容易になることが期待されています。
運転免許証や国家資格証、お薬手帳、介護保険被保険者証、障害者手帳、母子健康手帳、ハローワークカード、在留カードなどが対象です。
この流れはデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づく「マイナンバーカードを活用した各種カード等のデジタル化等に向けた工程表」に従って推進されています(令和4年6月7日閣議決定)。
令和5年からは「マイナポータル」を活用した、スマートフォン用の電子証明書が搭載されたサービスが提供されるようになりました。マイナポータルの実装により、オンライン申請や行政機関が保有する個人情報の閲覧・取得、お知らせの通知がスマートフォンのような個人デバイスで手軽におこなえます。
防災関連では、被災者支援業務におけるマイナンバーの活用が注目されています。被災者の負担軽減や行政の業務迅速化を目的として、内閣府では「クラウド型被災者支援システム」を構築し、令和4年度からその運用を開始しました。これにより、被災者支援を効果的、かつ、迅速におこなえることが期待されています。
防災におけるマイナンバーの活用

防災におけるマイナンバーの活用では、避難所受付システムや避難所管理の効率化が挙げられます。
マイナンバーを活用した避難所受付システムの導入メリット
マイナンバーを活用した避難所受付システムの導入には多くのメリットがあります。
まず、入所や退所時の手続きの大幅な効率化が可能です。従来の手書きによる受付管理は、どうしても非効率的で時間がかかりました。読みにくさや誤記入のような人的ミスも発生しがちです。
しかし、マイナンバーカードのICチップを読み込むことで、受付手続きが迅速、かつ正確におこなえるようになります。ICチップには個人の基本情報や証明書が記録されています。専用デバイスでの短時間の読み取りによって、手続きがスムーズに進むでしょう。
ICチップの読み込みを活用すれば、手書きで起こり得る人的ミスもかなり削減できるでしょう。混乱や待ち時間の削減が期待され、避難者、受付担当者の双方が負担を軽減できるようになります。
さらに、クラウド上で情報が一元管理されることで、避難所ごとの収容人数や男女・世帯数など重要な情報が容易に確認・共有しやすくなることも大きなメリットです。
避難所の状況をリアルタイムで把握し、必要な支援や物資の供給が効率的、効果的におこなえるようになります。また、行政や関係機関とデータをすぐに共有できるため、円滑な情報連携も可能です。
このようなシステムの導入は、災害時における受付業務の迅速化や正確性を向上させるだけでなく、緊急時の円滑な運用や避難者の安全確保にも大きく貢献します。
効率的、統合的な対応が可能になるこの避難所受付システムは、災害時の被災者支援体制を大幅に向上させるでしょう。
避難所管理の効率化に向けたマイナンバーの活用方法
マイナンバーを活用した避難所管理の効率化は、受付業務の混雑緩和や支援体制の最適化など、数多くのメリットがあります。
まず、受付業務の効率化により、避難所を運営する人員をほかの業務や支援活動に振り分けることが可能です。
たとえば前述の通り、ICチップ内蔵のマイナンバーカードを使うことにより、受付業務の迅速化が促進されるようになります。
それに加え、避難所に滞在する人数をリアルタイムで把握できるようになることも大きなメリットです。正確な人数の把握は、支援物資の必要量を的確に把握することにもつながります。無駄や不足が発生しにくくなり、安定した供給が実現するでしょう。
また、避難所ごとの収容人数や男女・世帯の構成などが簡単に把握できるため、行政やほかの避難所との連携がスムーズに進みます。
効果的な情報共有と連携は、被災した状況下で取り残される人や地域を出さないために不可欠な要素です。災害時において的確な支援が必要とされる中、マイナンバーを活用した避難所管理は、従来よりも進化した被災者支援体制を整えられるようになるでしょう。
マイナンバーの防災への活用事例紹介
実際にマイナンバーを防災面で活用している事例をご紹介します。
災害時のマイナンバーを活用した情報共有システム
宮崎県都城市では「デジタルケア避難所」を導入しました。避難所の管理運営をデジタル化することにより、業務効率化と地域住民の安心感を両立させる試みです。
デジタルケア避難所では、受付で「書かずに入所」が可能になっています。デジタルが得意な人はもちろん、デジタルが苦手な人でもマイナンバーカードを利用した受付手続きを踏むことにより、スムーズに避難所への入所が可能です。
また、避難所の混雑状況をリアルタイムで地域住民が確認できること、被災情報や物資の在庫、今後の需要予測の情報などを共有しやすいことも重要視されています。
情報の共有は避難人数や災害状況を外部からも確認しやすいメリットがあり、マスコミや情報を必要とする人々への情報提供が容易になる点にも注目です。
マイナンバーを利用した迅速な避難者の特定と保護
秋田県美郷町では、近年の豪雨による河川氾濫に備え、積極的にマイナンバーを活用した避難所受付サービスを取り入れています。地域住民の高齢化が進んでいることもあり、災害時における避難行動支援が急務という問題もあるようです。
マイナンバーカードを利用した避難所受付サービスは、前述の通り、避難所への迅速な入所や避難所状況の管理が可能になります。リアルタイムで避難者名簿の作成も可能になるため、「誰がどこにいるか」の確認が容易になることは、災害時において非常に重要です。
また、作成した避難者名簿の確認権限を自治体職員のみに限定している点にも注目です。マイナンバーカードの情報は多くの個人情報を搭載しており、見られることをためらう人もいるのではないでしょうか。
そういった人でも、確認権限の制限によってプライバシーを守りやすくなります。より安心して避難所を利用できるようになるでしょう。
避難所の名簿作成や支援物資の配布などに活用
神奈川県小田原市では、デジタル庁と提携し、大規模な実証実験をおこないました。震災が発生し、県内の80カ所に避難所が開設されたという想定で避難所運営を検証したのです。
その結果、名簿作成や支援物資の適切な配布において、マイナンバーカードを利用した避難所受付はアナログ受付よりも有用であるという見方が強くなりました。
マイナンバーを利用した防災システムの確立は、国が力を入れて推進している項目です。今後の検証や新たな提案、方針の発表にも注目しましょう。

マイナンバー防災システムの導入に向けた課題と解決策

マイナンバーを活用した防災システムの導入にはいくつかの課題があります。とくにプライバシー保護の確保、マイナンバーの適切な管理などに対する対策は重要です。
プライバシー保護の確保に向けた対策
どのようなシステムの運用においても、プライバシー保護は非常に重要です。
災害時には被災者の氏名や居場所などがさまざまな機関で共有されるため、個人情報保護の徹底が不可欠になるでしょう。
その対策として、事前(平時)に地域住民自身で個人情報が登録でき、かつ、第三者の利用を許可するか否かを設定できる機能を搭載したシステムの導入が望まれます。
マイナンバーの適切な管理と安全性の確保
マイナンバーの適切な管理と安全性の確保も求められます。マイナンバーは個人情報が集約されているため、流出防止や安全性の確保が必要です。
その対策として、個人情報保護委員会の指針や「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」などを参照し、これに準ずる指針の遵守が不可欠になります。行政職員はこれらの指針を周知し、適切な取り扱いを徹底するよう努めましょう。
自治体におけるマイナンバー防災システムの導入への具体的な手順
各自治体でマイナンバーを活用した防災システムを導入する際には、どのような手順が望ましいのでしょうか。
導入前に行うべき事前調査と準備
避難所受付システムの導入に先立ち、住民基本台帳や福祉関係システムからのデータ取得を行い、システムに統合するデータ連携は欠かせません。
総務省が示す「地域情報プラットフォーム標準仕様」では、「避難行動要支援者名簿管理」に係る標準仕様、「被災者台帳管理」に係る標準仕様などの仕様が標準化されています。このような適切なシステムを選択することで、導入プロセスが迅速、かつ、円滑に進行するでしょう。
避難所受付システムの構築と運用方法の解説
避難所受付システムの構築と運用には、地域住民への周知や事前準備が不可欠です。システム整備だけでなく、平時の準備が重要であることは間違いありません。住民にシステムへの事前登録を促進することにより、災害時にスムーズな受付が可能になります。
また、どのような状況でも運用できるよう、運用メンバーの属人化を防ぐ必要もあります。そのためには特定の部署に限らず、幅広い部署の職員へ周知や研修をおこなうべきです。多くの職員がシステムを習熟し、協力体制が確立された状態で災害に備える姿勢が重要になります。
このような備えは、避難所受付システムの効果的な活用を実現し、地域の安全確保をより強化することにつながるでしょう。
避難所受付システムについての提案
避難所受付システムを導入することで、職員間の情報共有も容易になるほか、時間を取られる受付業務も効率化できるため住民のみなさんにもメリットがあります。
いちからの構築には時間と費用がかかりますので、パッケージ化され、定額で利用できるサービスの導入がおすすめです。
コストと手間を抑えつつ、主要な機能が揃ったシステムの導入が可能となります。





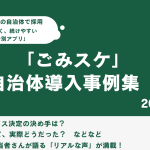
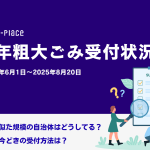



-150x150.jpg)



