地方創生にはさまざまな種類、方法があります。各自治体が取り組む際、どのような点が注目されているのでしょうか。
この記事では、地方創生の基本知識や取り組みジャンル、取り組み事例などを交え、地方創生を成功させるために役立つ方法などを紹介します。
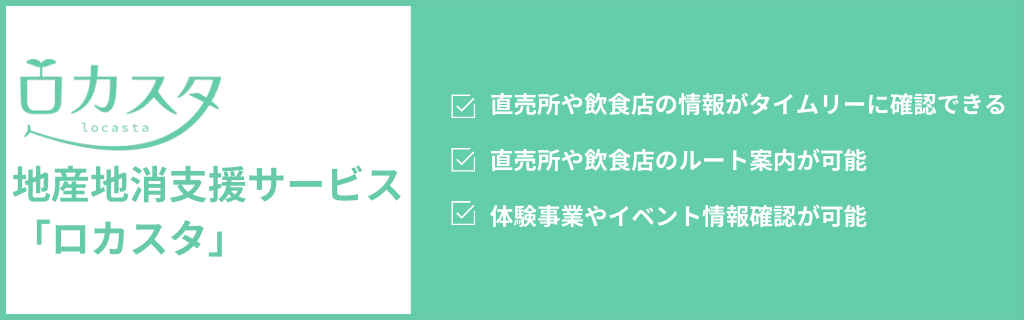
そもそも地方創生って?なぜ注目されてるの?

地方創生という言葉は広く知られるようになりましたが、その背景や意義を正しく理解することで、より効果的な活動につなげられます。
ここでは、地方創生の基本について改めて見てみましょう。
地方創生の歴史
地方創生は、2014年に「まち・ひと・しごと創生本部」が設けられたことで国の重点政策となりました。
全国の自治体は「地方版総合戦略」を作り、地域の課題に合わせた取り組みを進めています。
現在も細かい部分の変更を加えつつ、この枠組みは続いており、国と自治体が連携して地方の活性化に取り組んでいます。
人口減少・少子高齢化の加速
地方では、若者の都市流出と高齢化の進行により、労働力不足や生活インフラの維持困難といった問題が深刻化しています。
医療・福祉の人材確保や空き家の増加も課題となり、地域社会の存続が問われる状況です。
このような構造的ともいえる問題に対応するため、持続可能なまちづくりとしての地方創生が求められています。
地域課題の複雑化と、自治体への期待の高まり
人口流出による過疎化、産業衰退、災害リスクへの備え、インフラ問題など、地域課題は多様化・複雑化しています。
こういった状況に対応するためには、地域の事情を理解している自治体の自発的な取り組みが欠かせません。
該当する地域の自治体には実行力と創造力が求められ、地方創生はその中心的な取り組みになっています。
地方創生を推進する法律と政策
地方創生は、2014年に施行された「まち・ひと・しごと創生法」を柱として制度的に推進されるようになりました。
この法律に基づき、自治体ごとに総合戦略が策定され、国は交付金や人材派遣、官民連携支援などを通じて地域の取り組みをサポートしています。
現在も制度の見直しや重点支援の分野調整を行いながら、実効性のある施策が進められています。
自治体による戦略策定の流れ
各自治体が地方創生を進めるためには、戦略的な計画の策定が不可欠です。このプロセスは、まず地域の特性や現状を詳細に分析することから始まります。地域の強みや課題を明確にすることで、具体的な目標を設定し、それに基づいた施策を考案します。次に、地域住民や企業、行政機関との協力体制を築き、意見を集約しながら計画を練り上げます。具体例として、ある自治体では観光資源を活用した地域活性化を目指し、宿泊施設の整備やイベントの開催を計画に組み込んでいます。このように、地域の特性を活かした実効性のある戦略を策定することが、成功の鍵となります。最後に、策定した計画を実行に移し、進捗を常にチェックしながら柔軟に対応することが求められます。こうした流れを通じて、自治体は持続可能な地域発展を目指します。
地方創生とSDGsの関係
地方創生とSDGsの関係
地方創生は地域の活性化を目指す取り組みであり、SDGs(持続可能な開発目標)とは密接に関連しています。SDGsは、貧困の削減、教育の質向上、経済成長の促進など、17の目標を掲げており、これらは地域の課題解決に直結しています。例えば、地域の産業を振興し雇用を創出することは、SDGsの「働きがいも経済成長も」に貢献します。また、環境保護活動を通じて「気候変動に具体的な対策を」の目標にも寄与できます。地域全体でSDGsを意識した活動を展開することで、地方創生の効果を高め、持続可能な社会の実現に向けた一歩を踏み出すことができます。これにより、地域の魅力を高め、住民の生活満足度を向上させることが可能となります。
SDGsとは?
SDGs(持続可能な開発目標)とは、2015年に国際連合が定めた、2030年までに達成すべき17の目標のことです。これらの目標は、貧困の撲滅、教育の質の向上、気候変動への対応など、地球規模での社会課題を解決するために設定されています。各目標は具体的なターゲットを含んでおり、国や地域、企業がそれぞれの役割を果たすことが求められています。地方創生においても、地域資源を活用し、持続可能な経済や社会の構築を目指すことが重要です。例えば、再生可能エネルギーの導入や地域特産品のブランド化は、SDGsの目標と密接に関連しており、これらを進めることで地域の活性化と持続可能性を両立できます。SDGsを理解し、地域の特性に合わせた取り組みを行うことで、地方創生の効果を最大化することが可能です。
地方創生SDGs官民連携プラットフォームの役割と活動
地方創生SDGs官民連携プラットフォームは、地方自治体、企業、NPOなどが協力して地域の課題解決を図るための枠組みを提供しています。このプラットフォームは、SDGsの目標を地域レベルで実現するために、各ステークホルダーが情報を共有し、連携を強化する場として重要な役割を果たしています。具体的には、地域の特性に応じたプロジェクトの企画・運営をサポートし、成功事例の共有やノウハウの提供を通じて、他地域への展開を促進します。例えば、再生可能エネルギーの導入や地域産品のブランド化といった取り組みが挙げられます。官民連携を進める際は、目標の明確化と役割分担の徹底が鍵となります。これにより、効率的かつ持続可能な地域活性化が期待できます。
地方創生の代表的な取り組みジャンル

地方創生の現場では、自治体が地域の特性を生かして多種多彩な分野に取り組んでいます。ここでは、地方創生事業における代表的なジャンルを紹介します。
移住・定住支援(UIターン促進)
都市部から地方への移住を促す「UIターン支援」は、地方創生の中心的な取り組みです。
仕事や住まいの支援、移住体験プログラム、子育て環境の情報提供などを通して、移住希望者の疑問や不安を解消し、定住につなげる工夫が各地で進められています。
特に若年層や子育て世代の獲得は、地域の持続性を支える重要な要素といえるでしょう。
地域産業活性(農業・環境・ものづくり)
地域に根ざした産業を活性化することは、経済的自立や発展を目指すうえで欠かせません。
農産物のブランド化、地場のものづくり技術の継承、再生可能エネルギー導入など、地域資源を生かした取り組みが進められています。
これにより地域経済の循環が生まれ、働く場の確保や地域内消費の促進にもつながるようになった事例も少なくありません。
デジタル活用(スマートシティ・デジタル田園都市)
ICT(情報通信技術)を活用したまちづくりも地方創生の柱のひとつです。行政サービスの効率化、交通や医療のデジタル化、防災システムの導入などが進められ、「スマートシティ」や「デジタル田園都市国家構想」が全国に広がるようになりました。
都市部に依存せず、地方でも便利で豊かに暮らせる環境づくりが期待されています。
関係人口づくり(交流・副業人材)
地域に一時的・継続的に関わる人々、いわゆる「関係人口」の育成も注目されています。「観光以上移住未満」ということもある関係です。
観光・交流イベント、ワーケーション、副業や地域起業の促進などを通して、地域外の人材が地域づくりに継続的に関わる機会が増えています。
定住に至らなくても、地域との多様な関わりが地域の活力を支える重要な一面です。
子育て・教育支援
若い世代の流入と定住を促すには、子育てや教育環境の整備も重要です。
保育所や学校の充実、学童保育、子育て支援センターの設置、ICT教育の導入など、地域全体で子育てを支える体制づくりが進んでいます。
安心して子どもを育てられる環境があることは、移住希望者にとっても大きな決め手になるでしょう。
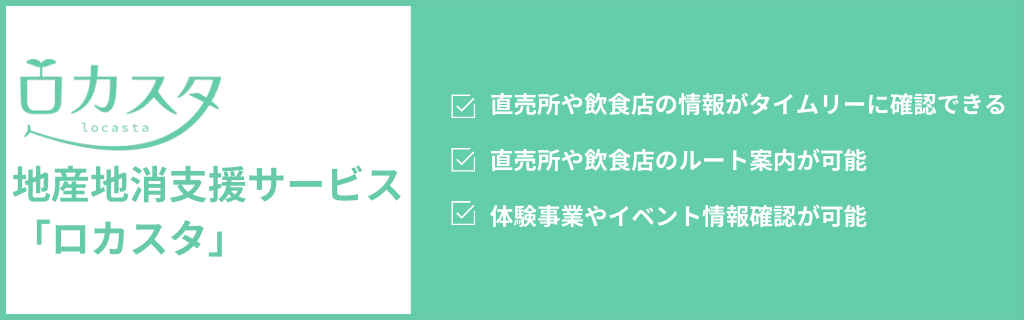
現場で進んでいる注目の取り組み5選

地方創生の現場では、各地の自治体が独自の工夫を凝らした取り組みを行っています。
ここでは、よく見られる代表的な施策を5つ紹介します。
①空き家バンクの活用で移住者増
空き家バンクは、地域の空き家情報をデータベース化して公開し、移住希望者に住まいを提供する仕組みです。
提供するだけではなく、自治体が仲介や改修補助などのサポートも行うことにより、空き家の有効活用と移住者の増加を同時に実現しやすくなっています。
空き家が多い地域では、新たな住民や起業家の受け入れ手段として定番となっています。
②ワーケーション誘致プログラム
ワーケーションは、観光地や自然豊かな地域で「働きながら休暇を楽しむ」新しい働き方です。
自治体では、コワーキングスペースの整備や宿泊施設との連携、体験プログラムの提供などを進め、都市部企業やリモートワーカーの誘致に力を入れています。
地域経済の活性化と関係人口の増加を同時に目指す施策です。
③アプリでごみ収集に関する情報発信
ごみ収集に関する情報をアプリで手軽に発信する自治体が増えています。
収集日や分別ルール、臨時回収などをリアルタイムで住民に知らせることで、ごみ出しのミスやトラブルを減らし、住民の生活環境維持やサービスの向上につなげています。
こうしたデジタル活用は、住民の利便性向上と行政の効率化に貢献しているといえるでしょう。
④関係人口を「地域のファン」として育てる広報戦略
地域と継続的に関わる「関係人口」を増やすため、自治体は地域の魅力や体験を発信する広報に力を入れています。
SNSやオンラインイベント、ふるさと納税を活用した情報発信などにより、リピーターや地域のファンを獲得。
住民以外の多様な人々が地域づくりに参画する流れを生み出しています。
⑤地域での起業支援
地域課題の解決や新しい価値の創出につなげるため、起業支援に積極的な自治体が増えています。
起業相談窓口の設置、「社会性」「事業性」「必要性」の視点を持つ起業に創業資金の助成、専門家による伴走支援、起業家向け交流イベントなど、多彩な支援策を用意。
地域に根差したビジネスが増えることで、雇用や経済の循環にも好影響を与えています。
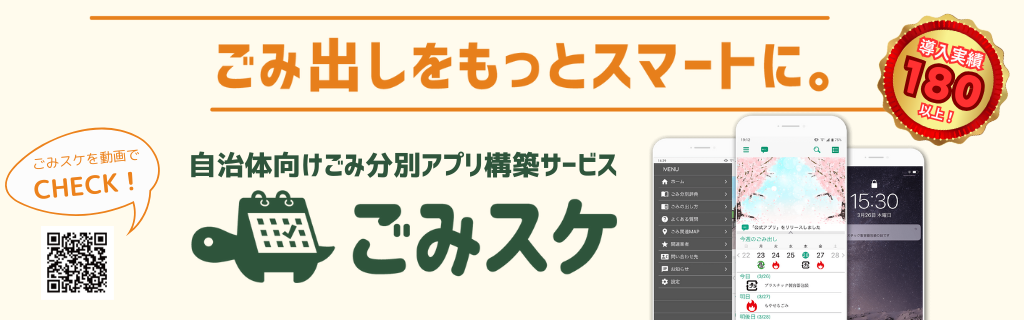
成功するための地方創生プロジェクトのポイント

地方創生の取り組みを成功させるには、計画的な進行と柔軟な対応が必要です。
ここでは、実践で意識すべき重要なポイントを整理してみましょう。
専門家のアドバイスを活用
地方創生プロジェクトでは、地域づくりやまちづくりの専門家、各分野のコンサルタントなど外部の知見を取り入れることで、効果的な戦略を立てやすくなります。
最新の事例や課題解決ノウハウを参考にすることで、地域の独自性を生かしつつ現実的な計画が進めやすくなるでしょう。
外部の視点は客観的な評価や事業推進の後押しにも役立ちます。コミュニケーションを意識しながら、有識者との会話を試みましょう。
地域資源を効果的に活用
地域にしかない資源や魅力を最大限に生かすことも、成功する地方創生の基本的な視点になります。
特産品や観光資源、自然や歴史など、地域固有の強みを掘り起こし、情報発信や体験事業に結びつけることで、多くの人の関心を集め、地域を発展させるきっかけになるでしょう。
住民の協力も得ながら地域の魅力を再発見し、ブランド力を高める工夫が求められます。
民間企業との協力体制の構築
民間企業との連携は、資金やノウハウ、人材など多様なリソースの活用につながります。
地域の課題解決や新たな事業の立ち上げ、販路拡大などでも企業の力を生かすケースが増えています。
自治体と企業が目的を共有し、互いの強みを持ち寄ることで、持続可能なプロジェクト運営が実現しやすくなるでしょう。
地方創生は”小さな一歩”から!
地方創生は大きな計画を実行していく必要のあるプロジェクトですが、一方では、日々の小さな行動や挑戦の積み重ねも大切です。
ここでは、実践の最初の一歩に注目してみましょう。
まずは小さなチャレンジを
いきなり大きなプロジェクトを目指すよりも、まずはできることから始めるのが大切です。
たとえば、身近な課題解決やイベントの開催など、小さな成功体験が地域住民の自信につながります。
最初は失敗や試行錯誤も多いですが、継続することで地域内に前向きな雰囲気が生まれ、少しずつ成果が広がっていきます。
最初は小さなことやできることから始め、成功体験を積み重ねてステップアップを目指しましょう。
地域の強みを見つけて、つなぐ
自分たちの自治体の魅力や資源を改めて見直し、外からの視点も参考にしながら強みを見つけていきましょう。
そのうえで、人や団体、企業、他の地域と連携し、資源をつなげて新しい価値を生み出し、アピールする工夫が求められます。
多様なアイディアやネットワークが、地域を元気にする原動力になるでしょう。
行政も民間も”それぞれの役割”で関われる
地方創生は行政だけのものではありません。
自治体が計画や制度の整備を進める一方で、民間企業や地域住民も自分たちの得意分野や役割で参画できます。
それぞれが強みを発揮し、無理のない範囲で関わることで、地域全体の一体感と持続性が高まります。
とはいえ、どうしても自治体が主導になることは否定できません。
民間企業や地域住民が「参加したい」「アイディアを出したい」と思うような環境を整備しながら、地方創生を成功させる土台を作り、実践していきましょう。
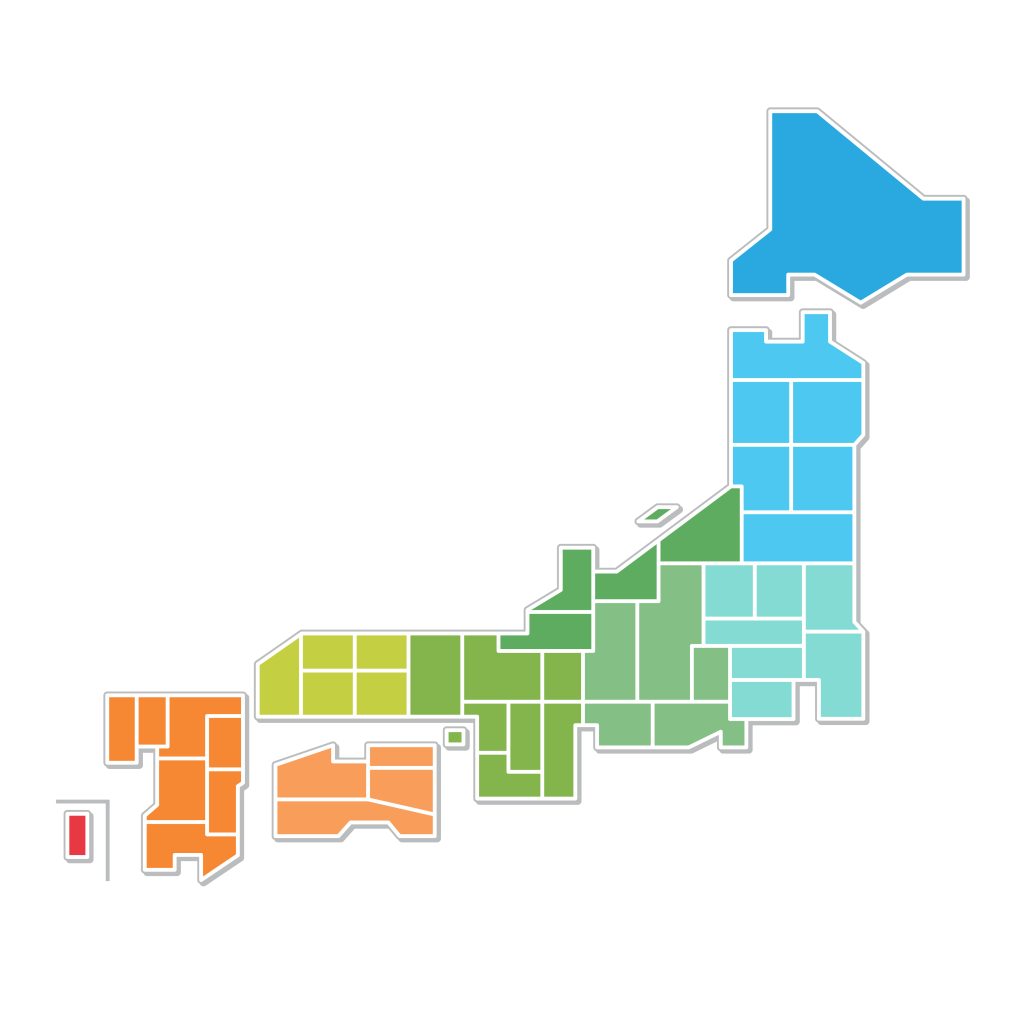
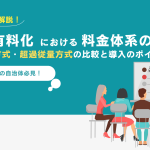


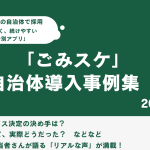
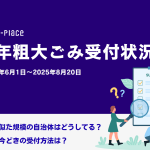
-150x150.jpg)




