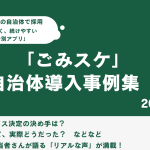「揺れたら、すぐ高台へ」――。
この、たった10文字にも満たないシンプルな行動を住民に徹底してもらうことが、いかに難問か。 連日のようにハザードマップの見直しを行い、避難訓練の企画に頭を悩ませる自治体の防災担当者の皆様なら、きっと痛感されているはずです。
東日本大震災から10余年。防潮堤の整備やハザードマップの更新など、アナログな防災インフラは着実に強固なものとなりました。しかし、その一方で「避難訓練のマンネリ化」や「情報の到達率」といった、ソフト面の壁が立ちはだかっています。迫りくる南海トラフ巨大地震に対し、従来の対策だけで本当に「逃げ遅れゼロ」は達成できるのか。
今、自治体に求められているのは、これまでの「ハード対策」という土台の上に、デジタルの力を掛け合わせ、一人ひとりの避難行動を最適化する「防災DX」へのパラダイムシフトです。
本記事では、過去の教訓から導き出された最新の津波対策から、現場の負担を劇的に減らすデジタル活用の最前線まで、実務者の視点で解き明かします。

津波災害の「正体」を再確認する
津波は日本各地で繰り返し発生し、甚大な被害をもたらしてきました。
自治体の防災担当が現状を理解し、対策を進めるためには、津波の特性と国内の災害事例の把握が欠かせません。以下に津波被害について改めて整理しました。
日本を取り巻く津波災害の現状
「速さ」のリアリティ: 深海ではジェット機並みの秒速数百メートルで進み、陸に近づくと一気に壁となって盛り上がります。気象庁の警報が届く数分の間に、すでに勝負は決まっているケースも珍しくありません。
「執拗な」繰り返し: 第一波が最大とは限らず、後から来る波がさらに高くなる。この「時間差の罠」を理解してもらうことが、第一波が到着した後の「戻り被災」を防ぐ鍵となります。
注意報の「殺傷力」: 「注意報レベルだから海岸を見に行く」という行動をどう止めるか。1メートル弱の津波でも、人間を押し流し、命を奪うには十分すぎる威力があることを、私たちは伝え続けなければなりません。
過去の教訓を「想定外」で終わらせない
過去の被災事例は、未来の計画書そのものです。特に東日本大震災以降、自治体の施策は大きな転換期を迎えました。
「垂直避難」へのシフト: 「高台がないから逃げられない」という声に応え、避難ビルや避難タワーの整備が重点施策となりました。これは、法律(津波防災地域づくり法)に基づいた「命を守るためのインフラ」への投資です。
「徒歩避難」という大原則: 被災地で発生した深刻な渋滞。その教訓から、現在は「車避難」をいかに抑制し、「早期の徒歩避難」を促すかが、地域防災計画の心臓部となっています。
「想定」を疑う姿勢: 近年、東日本大震災以外でも津波が確認されています。「ハザードマップの外だから安全」という思い込みを排し、L2(最大クラス)を見据えた警戒区域の指定が、自治体の新たなスタンダードとなりつつあります。
自治体が取り組むべき津波対策とは?

津波被害を最小化するためには、地域の特性に応じた多様なアプローチが必要です。しかし、予算もリソースも有限。自治体には「どれだけ実効性を持たせられるか」という戦略的な視点が求められます。
「夜間・悪天候」を想定した避難路のブラッシュアップ
避難路は、作って終わりではありません。災害は晴れた昼間に来るとは限らないからです。
視認性の極大化: 国土交通省の指針に基づき、高台への最短ルートを確保するのは大前提。その上で、停電時でも機能する蓄光式看板やソーラー照明を、特に「曲がり角」や「分岐点」へ重点配置し、住民を迷わせない工夫が求められます。
「徒歩避難」への強制力: 浸水想定区域内での車両避難は、渋滞を引き起こし、逃げ遅れの最大の要因となります。「徒歩の方が確実で早い」という定量的エビデンスを住民に提示し、心理的な「車依存」を脱却させる啓発が必要です。
施設の整備:沿岸部の「最後の砦」を確保する
高台が乏しい沿岸部において、津波避難ビルや避難タワーは、文字通り「最後の砦」となります。
官民連携の加速: 公共施設だけでなく、民間の堅牢なマンションやオフィスビルを指定し、協定を結ぶこと。これはコストを抑えつつ避難可能人数を爆発的に増やす、極めて効率的な戦略です。
耐震・耐波性能の担保: 「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、施設の構造強度を確認し、万が一の来襲時にも崩壊しない「安心の根拠」を住民に示しましょう。
「配って終わり」にしないハザードマップの活用術
ハザードマップは「リスクの可視化」ツールですが、今の自治体に求められているのは「行動を喚起する地図」へのアップデートです。
自分ごと化できる工夫: 浸水域を示すだけでなく、「自宅から避難所まで徒歩で何分かかるか」を書き込める余白を作る。
避難の「見える化」: 住民が日常的に目にする場所に、浸水想定の高さを記した「津波標識」を設置するなど、マップの内容を街中の景色とリンクさせることが、避難のスイッチを押しやすくします。
「マンネリ」を打破する防災訓練・教育
「いつもの訓練」では、本当の危機に対応できません。
訓練シチュエーションの多様化: 道路が寸断された、夜間である、スマートフォンの電源が切れた……。あえて「最悪の状況」をシミュレーションさせることで、住民のレジリエンス(適応力)を高めます。
世代間シェア: 学校教育と連携し、子供たちが学んだ知識を家庭に持ち帰らせる。これは、最も防災意識が届きにくい現役世代への、有効なアプローチとなります。
避難計画:実効性を担保する「集大成」
数々の施策の集大成となるのが避難計画です。
「0秒避難」の浸透: 警報を待っていては遅い。揺れを感じた瞬間に「どのルートで、どの施設へ、誰と逃げるか」がオートマチックに決まっている状態。その判断を支えるのが、自治体が策定する地域ごとの詳細な避難計画です。
情報の多層性: テレビやスマホが使えない状況を想定し、地域コミュニティやサイレン、広報車など、情報の「届け方」を幾重にも重ねる設計が、自治体としての誠実さと言えます。
自治体の先行事例に学ぶ「地域最適化」のヒント
理論をどう形にするか。津波リスクと正面から向き合う2つの県、神奈川県と静岡県の「攻め」の施策を見てみましょう。
神奈川県による津波災害警戒区域の指定
神奈川県は「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、津波災害警戒区域を指定しています。
区域ごとに避難施設を明示し、徒歩避難を基本にする計画を策定しました。
また、津波浸水想定図やハザードマップを住民に公開し、避難路や危険区域を分かりやすく示しています。
静岡県における港湾部の防潮施設整備
静岡県は港湾部を対象に津波や高潮への備えを強化しています。
港湾施設や海岸防潮施設の耐震化を進めるとともに、近隣の地域住民が迅速に避難できるよう、津波避難施設や避難路を整備しました。
これにより、沿岸部で高台が遠い地域においても短時間で安全な場所へ移動できる環境が整い、防災力の向上につながっています。
「等身大」の防災DX:デジタルで現場の負担を減らす

津波対策を強化するうえで、近年注目されているのがデジタル技術の導入です。
混乱する現場で「担当者が判断を下すための余裕」を生み出す可能性を秘めているシステムの導入。背伸びをしない、実務に即したデジタル活用を考えていきましょう。
デジタルツールを活用した情報伝達
津波は1分1秒が命取りになります。最新の情報を、いかに住民の「目と耳」に直接届けるかが勝負です。
スマホを「動く防災無線」に: 公式LINEや防災アプリは、防災無線の音声が届かない遮音性の高い住宅や、豪雨の中でも確実に情報をプッシュ配信できます。
情報のユニバーサルデザイン: 聴覚障害者の方へは文字、外国人観光客へは多言語での自動配信。複数のデジタルチャネルを連動させる「情報の多重化」が、現場で「誰一人取り残さない」ことにつながります。
避難所運営のカオスを鎮める「デジタル管理」
津波発生後には多数の住民が避難所に集まるため、迅速で効率的な管理が求められます。
「紙とFAX」からの脱却: QRコードを用いた受付システムを導入すれば、数時間かかっていた名簿集計が数秒で完了します。
情報のリアルタイム共有: 「どの避難所にあと何人入れるか」「どこの水が足りないか」をクラウドで一元管理。関係者間で状況を可視化できれば、支援物資のミスマッチという、あの不毛な混乱を劇的に減らすことができます。
まとめ:未来の「よかった」のために
神奈川県や静岡県の事例が示す通り、地域特性に合わせた警戒区域の指定やインフラ整備は、着実に住民を守る力となっています。
しかし、技術が進歩し、法律が整っても、最後に命を救うのは「住民一人ひとりの避難の決断」です。自治体の役割は、その判断を支えるための「迷わせない、空振らせない仕組み」を、デジタルとアナログの両面で磨き続けることに他なりません。
「あの時、対策を打っておいてよかった」 次の災害が来たとき、そう胸を張れる地域づくりを。私たちの手元にある避難計画を、今この瞬間からアップデートしていきましょう。