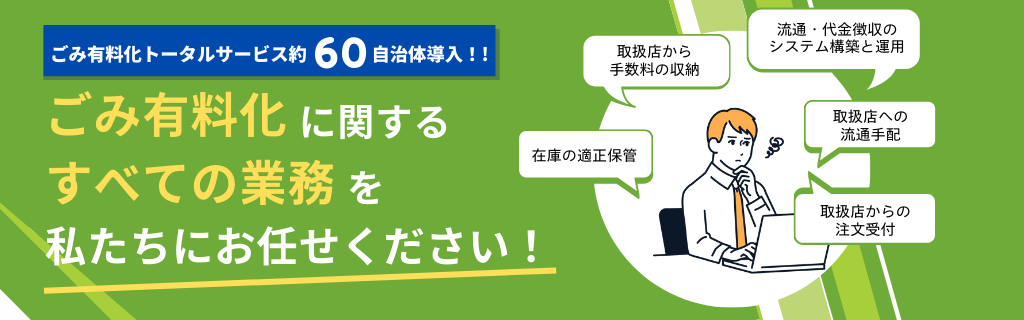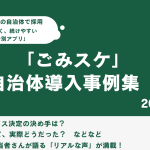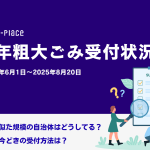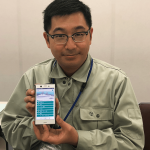ごみ減量資料室代表・東洋大学名誉教授
山谷 修作
自治体が新たな制度を導入した場合、数年程度の間隔でその効果や問題点などを検証し、必要に応じて見直しを加えてより良いものにしていくPDCAサイクルの取組みを行うことが一般的である。ごみ有料化については環境省の「一般廃棄物処理有料化の手引き」にもおおむね5年に一度の頻度で制度見直しを行うとある。だが、実際に有料化実施の数年後に本格的な制度検証に踏み込んだ自治体は、ごくわずかにとどまっている。
そうした状況のもと、昨年度、有料化実施から5年目を迎えた神奈川県海老名市が有料化と戸別収集の検証作業を行う家庭系ごみ専門部会を立ち上げた。この部会は、有料化の実施にあたり制度設計の検討作業を行った環境審議会下部組織で、筆者が部会長を務めている。市が手間のかかる検証作業に踏み込むことについては伏線が敷かれていた。有料化実施に必要な条例改正を議決するにあたり、市議会から表1に示すような12項目の付帯決議が付けられていたのである。市は、議会の付帯決議の各項目に対応すること、とりわけ決議項目4の「導入後も適宜効果を検証し施策の見直しを行うこと」を求められていたのであった。
【表1】市議会の付帯決議事項
- 戸別収集における各家庭の集積所など個別の対応を含め、周知を徹底すること。
- 家庭系ごみだけでなく、事業系ごみについても、減量化対策を強化すること。
- 同時期に実施予定の消費税増税による負担増に対して、家庭系ごみ指定収集袋の無料配布などさまざまな手法を検討し、対策を講じること。
- 導入後も適宜効果を検証し、施策の見直しを行うこと。
- 不法投棄対策の強化を行うこと。
- 外国人居住者等への丁寧な対応を行うこと。
- 集積所が設置されていない小規模な集合住宅への集積所の設置支援と指導の徹底を行うこと。
- 大規模集合住宅に対して、ごみ減量化をさらに推進した場合の支援など対応を検討すること。
- 高齢者および障害者の雇用等に関しては、適性に応じた形で進めること。
- 民間業者との連携をする際は、市内事業者に対して十分な配慮を行うこと。
- 実施当初において示される予算規模の中での実施とし、今後は歳出の削減を行うこと。
- (一部事務組合を構成する:筆者注)座間市および綾瀬市に対してさらなるごみの減量化を求めるとともに、有料化の導入を促すこと(組合の焼却施設は海老名市内:同)。
部会による有料化・戸別収集制度の検証作業は、市議会の付帯決議各事項に対する市の対応の検証評価、それに加えて表2に示す7項目について制度運用状況の検証と見直しの方向性の検討を行うこととされた。検証作業にあたっては、市が市内3,000世帯を対象として2022年9月に実施した「家庭系ごみの一部有料化・戸別収集導入後アンケート調査」の結果が参考資料として役立てられた。
【表2】制度運用状況の検証事項
➀指定収集袋(手数料水準、新しいサイズの追加、素材の利用性とコストを踏まえた検討、燃やせるごみ・燃やせないごみ共通袋の検討、販売方法の検討)
➁ 有料化品目(燃やせないごみで無料の品目の検討)
➂収集方法(燃やせるごみ戸別収集制度の継続、資源物隔週収集)
④資源物(新たな資源化手法、資源物の収集方法などの検討)
⑤減免制度(対象世帯、配布枚数などの検討)
⑥支援制度(生ごみ処理機購入補助)
⑦その他の取組み(集合住宅・高齢者等支援)
まず、市議会付帯決議について。項目ごとに行政サイドの対応とその評価、部会委員サイドの評価について、字数の都合により項目1~4に絞って簡潔に確認しておこう(注)。
(注)項目5~12についての行政の取組みと自己評価については、市ホームページトップから入り「市政・ビジネス」→「審議会」→「環境審議会家庭系ごみ専門部会の概要」→「第2回専門部会(2024年4月23日開催)資料」で確認されたい。なお、その資料中、専門部会の評価欄については、委員合意のもとに一部変更されている。
【項目1】については、市内全域の戸建て住宅約27,500戸を1軒ずつ事前調査して排出場所を決めてその結果を通知し、併せて排出方法のお願いチラシをポスティングするなどきめ細かな周知活動を行っており、市、部会とも「十分に取り組んでいてかつ効果が出ている(◎)」と評価した。
【項目2】については、事業系ごみ減量化基本方針の策定、排出事業者への訪問指導、生ごみ処理機の導入支援、搬入手数料の見直しなどの取組み強化が行われ、行政の評価は「取り組んでいるが改善の余地がある(〇)」と控えめであったが、部会の評価の方は搬入手数料の二段階引き上げ改定を特に高く評価して「◎」に上方修正した。
【項目3】については、有料化実施の前月に指定収集袋のサンプル袋(小サイズのお試し袋)を市内全戸に無料配布(引換券郵送、指定場所で引き換え)し、また生活保護受給世帯や児童扶養手当受給世帯などを対象に指定収集袋の減免制度を導入している。行政の評価はサンプル袋を配布することで購入間違いを防ぐことができたなどの理由で、また部会の方も減免対象が幅広く手厚いとして、どちらも「◎」評価とした。
【項目4】について、行政は広報紙のごみ特集号でごみ量や収支の報告を行っており、有料化・戸別収集実施後アンケート調査も実施している。行政の評価は見直しに向けて取り組んでいるとして「〇」であったが、部会委員の評価の方は有料化導入後の今回の効果検証が全国的に実施事例希な中で先駆的な取組みとして大きな意義を持つとして「◎」評価とした。
項目5以下の取組みと評価は省略するが、付帯決議対応スコアをまとめると、行政の評価が◎7項目、〇5項目、部会の評価が◎9項目、〇3項目であった。△(取組みが不十分)評価は皆無。環境審議会の答申には、付帯決議事項について、専門部会における判断として「事務局の取組みはおおむね的確になされた」とある。
次の制度運用状況の検証事項【表2】に移ろう。
まず、➀指定収集袋。その手数料については最もごみの減量効果が期待できる水準(1L=2円)を採用し、減量化に成功しており、現状維持が妥当と考えるとした。実際に、1人1日当たりの家庭系可燃ごみ排出量は、有料化実施前年度の2018年度との比較で、2023年度には20%減となっていた。サイズについては市民アンケートで現在のサイズ展開に満足とする意見が過半数を占めていたことから、変更不要と判断した。素材については、既存の製品以上に環境面に配慮した素材の研究を進め、適宜変更していくこととした。燃やせるごみ・燃やせないごみ共通袋については、適正排出の妨げとなる恐れから、導入しないとした。また販売方法について、バラ売りの導入が市民の利便性向上やプラスチック削減に効果があると指摘した。
次に、➁有料化品目。燃やせるごみについては減量化の観点から、無料品目を追加せず現状維持が妥当とした。一方、燃やせないごみについては、資源物として収集している品目の中で、資源化できていない品目の一部を有料の燃やせないごみへ変更する必要があるとした。
➂収集方法については、現状の燃やせるごみの戸別収集について排出者責任の明確化による減量化を図るため継続することが妥当とし、燃やせないごみ・資源物についてはコスト面と市民の利便性とを比較しながら慎重に検討する必要があるとした。
また、④資源物については、剪定枝の資源化量を増やす取組みとして、申請方法の見直しや排出条件の緩和などが必要とした。
⑤減免制度については、減免対象世帯の減量意識を高めるため、指定収集袋の配布方法や配布枚数を見直す必要があるとした。
また、⑥支援制度については、引き続き生ごみ処理機購入費用の助成を行い、減量化啓発に努める必要があるとし、また今後は脱炭素社会に向けて非電動式生ごみ処理機の普及率を向上させる取組みが重要と考えるとした。
そして、⑦その他の取組みとして、集積所を適正に管理する集合住宅を表彰する制度など、減量化や適正管理に効果が期待できる施策を採用すること、またごみ出しが困難な高齢者に対する支援について福祉部局と協力して充実させることとした。
以上が2024年度に海老名市が4回の専門部会を開催して、有料化・戸別収集制度の効果検証、見直し作業を行って得た結論の概要である。市はこの検証作業を通じて、議会の付帯決議事項に対する説明責任を果たすとともに、市民に対しては、さまざまな議論を呼んだ有料化導入について、その成果と課題、見直しの方向性をきちんと示すことができたと思う。
有料化自治体にあっては、検証作業を怠らずに、制度の効果や課題、見直しの方向性を浮き彫りにし、検証の結果を住民に情報公開して、有料化制度の改善と活性化につなげることをシン常識としたいものである。

山谷 修作Yamaya Shusaku
東洋大学名誉教授 ごみ減量資料室代表
中央大学大学院経済学研究科博士課程修了
経済学博士
1949年生まれ。専門は環境政策。特に廃棄物行政に詳しく、全国の自治体に足を運んでフィールドワークを実施。市町村アカデミーなどの研修講師を行う。「ごみ減量政策」「ごみ有料化」 など、著書多数。